1年に3度も値上げする商品が多い理由
「この1年で3度目の値上げです」と報道される食品が結構な数あります。値上げの理由は円安や物流の混乱などが原因ですが、原因を把握していたら1度に値上げを完了することができるはずです。
にもかかわらずメーカーが商品を小出しに値上げする背景にはメリット・デメリットをめぐる損得勘定があります。本稿ではこの点を開設したいと思います。
小出しにした方が顧客の抵抗感を回避しやすい
①いきなり3割値上げされた商品と、②1割ずつ3度値上げされた商品、どちらが「もうこの商品買うの辞める」と思いがちでしょうか。通常は①だと思います。
こうして値上げを小出しにすることで、「値上げは痛いけれどこの程度の値上げなら仕方ない」と顧客の不満を閾値に達しないよう調整しながら値上げを実現する点に小出しのメリットがあります。
値上げに対する感度分析ができる
値上げを小出しにすると、どの程度の値上げをしたらどの程度売上や利益に影響が生じるのか情報が入手できます。この情報をふまえて、次の値上げ戦略を練るなど細かな活動が可能となります。
価格が1単位増減した際に、売上や利益がどの程度変化するかを分析することを会計上、感度分析といいます。非常によく使用される手法で、実践的にはこれが大きなメリットとなります。
要因ごとに値上げの効果を割り振る
値上げの要因は様々ですが、1度にすべての要因で値上げする必要はなく、1つずつ順を追ってやっていくことも考えられます。例えば1つ目は仕入れ価格高騰の転嫁、2つ目は円安の影響、3つ目はそれい以外・・といった感じです。
こうして要因毎の効果測定ができると、その後の価格設定戦略に有効な情報も得られて経営に有用です。
小出し値上げのデメリット
小出し値上げにはデメリットもあります。頻繁な価格改定で、販売現場に混乱が生じる点が多いです。コンビニで値札のついていない商品が最近かなり増えたことに気づかれた方もいると思います。商品価格が頻繁に変わるため、店が値札の改訂に追いつかないのです。
こうした状況が続くと、「値段が違う」とか、「値札を見せない詐欺だ」などと余計なトラブルが生じてしまいがちで、現場のオペレーションに大きな負担をかけてしまうことがデメリットです。
まとめ
以上のように、小出しで値上げすることは、企業戦略的にメリットがいくつかありますが、現場、そして商品を購入する顧客に負担や混乱を生じさせるため、使い分けの判断は簡単ではありません。
当研究所では、経営に詳しい弁護士・公認会計士が、御社の適法かつ数値に基づいて有効な戦略策定をサポートいたします。下記よりお気軽にご相談ください。
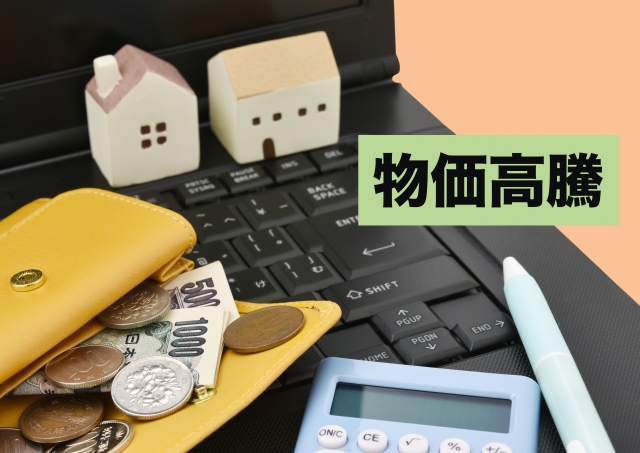


コメント